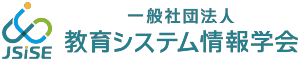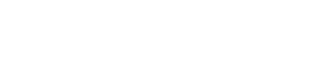Special Interest Group(SIG)提案募集
背景および目的
教育システム情報学会(JSiSE)では、教育システム情報学分野における多様な研究活動を推進し、本学会における研究コミュニティを活性化するため、2026年度より新たにSIG(Special Interest Group)制度を導入します。
SIGとは、教育システム情報学に関連する特定の研究テーマについて、学会員有志を中心に組織される自律的な研究グループです。学会としてこれを支援し、全国大会や学会誌等を通じた研究活動・成果発信を促進することで、持続可能な研究コミュニティの形成・拡大を図ります。
今回新設するSIG制度では、その活動規模や内容に応じて以下の2種を設けています。
SIGとは、教育システム情報学に関連する特定の研究テーマについて、学会員有志を中心に組織される自律的な研究グループです。学会としてこれを支援し、全国大会や学会誌等を通じた研究活動・成果発信を促進することで、持続可能な研究コミュニティの形成・拡大を図ります。
今回新設するSIG制度では、その活動規模や内容に応じて以下の2種を設けています。
第一種SIG
前年度に全国大会における企画セッションを実施し、かつ研究会における企画セッションを2回以上実施した優秀なSIGとして、学会からの財政的支援を申請することも可能であり、一定の規模感で積極的な活動を推進する研究コミュニティを形成していく種別(第二種SIGとしての活動実績を経て昇格)。
第二種SIG
全国大会もしくは研究会における年1回以上の企画セッションを軸に、比較的小規模かつ柔軟に研究コミュニティを形成していく種別。
上述の通り、第一種SIGは前年の実績に基づいて決定しますので、SIG設立の提案時に応募いただけるのは第二種SIGのみとなります。今回、2026年度からの活動開始にあたり、2025年末日を期限として、第二種SIGの提案を募集いたします。
募集対象
教育システム情報学の分野において、特定の研究テーマのもとでの革新的な技術開発や研究活動を行い、継続的なコミュニティ形成を目指すSIGの提案を募集します。
SIGの提案は、3名以上の本学会員からなる研究グループによるものとします。(なお、背景および目的にある通り、提案いただける種別は第二種SIGのみとなります。)
SIGの提案は、3名以上の本学会員からなる研究グループによるものとします。(なお、背景および目的にある通り、提案いただける種別は第二種SIGのみとなります。)
提案内容
募集にあたっては、指定の書式に従い、以下の項目を含めた提案書を提出してください。
- SIGの名称(正式名称(和),正式名称(英),略称[アルファベット2から5文字])
例)
和:SIG-教育システム情報学
英:SIG-Information and Systems in Education
略称:SIG-ISE - 提案者リスト(筆頭幹事・幹事・構成メンバー一覧)
- 本SIGにおける研究テーマの概要(学術的・社会的課題などの背景を含む)
- 本SIGのテーマのもとで共有したい学術的「問い」の例(複数可)
- 本SIGの活動によって、本学会において期待される成果
- 初回の企画セッションの企画案(開催タイトル、現時点での発表者一覧(最低3件))
- 年間活動スケジュール(4月~翌3月)
応募方法
提案書は以下のオンラインフォームにて提出してください。
※2026年度第二種SIGの受付は終了いたしました。2027年度の募集については2026年秋頃にご案内いたします。
第二種SIG提案フォーム
※本フォームでは、所定の書式のPDFとJSONファイルをご提出いただきます。
※本フォーム内に、これらのPDF・JSONファイルを作成するためのシステムへのリンクがありますので、これを用いてご作成ください。
提出期限:2025年12月31日
※2026年度第二種SIGの受付は終了いたしました。2027年度の募集については2026年秋頃にご案内いたします。
※本フォームでは、所定の書式のPDFとJSONファイルをご提出いただきます。
※本フォーム内に、これらのPDF・JSONファイルを作成するためのシステムへのリンクがありますので、これを用いてご作成ください。
提出期限:2025年12月31日
選考プロセス
1.書類審査(2026年1月上旬) ※必要に応じて面談審査を行うこともあります
2.採択発表(2026年1月下旬)
2.採択発表(2026年1月下旬)
SIGとして活動するメリット
SIGとして認定されると、以下のようなメリットがあります。
- 学会の公式な研究コミュニティとして位置付けられ、全国大会・研究会・学会誌などを通じて継続的に活動・成果発信が可能になります。
- 他のSIG、重点研究推進部会等との合同企画や連携特集を組みやすくなります。
- 学会ウェブサイトや広報でSIG活動が紹介され、学会員・外部の研究者への認知が高まります。
- 対外的に「教育システム情報学会(JSiSE)認定のSIG」として、助成金・共同研究申請等の際に活動基盤を示すことができます。
- 第一種SIGとして認定されれば、学会からの財政的支援(最大20万円/年を予定)を申請できるようになります。
支援について想定される主な使途(予定):
- 研究遂行に係る旅費等
- 会議費、レンタル費、研究遂行に係る消耗・機器備品費
- 研究遂行に必要な講師等の謝金(講師等を招聘する場合、会員の公益となるように位置づけることが求められます)
- その他、研究活性化委員会が必要と認めたもの
※財政的支援の用途については確約するものではございません。
SIGで期待される主体的活動
SIGは将来的に自律的・継続的な研究活動を展開し、学会における研究のハブとなることが期待されています。以下は義務ではありませんが、主体的に取り組んでいただきたい重要な活動です。
研究成果の創出と発信
SIGテーマに基づく成果(論文、教材、システム等)を継続的に生み出し、学会や他学会で発表・出版する。
コミュニティ形成と連携
関心を共有する研究者・実践者を巻き込み、議論や共同活動を通じてネットワークを育てる。
広報と情報発信
WebサイトやSNS、資料を通じてSIG活動の価値を学会内外に伝える。
組織体制の整備と将来像の明確化
ビジョン・ミッションを整理し、SIGとしての持続可能な活動計画や組織を確立する。
SIGの年度審査
第一種SIG、第二種SIGともに当該年度の活動実績や活動内容に基づき、次年度のSIG種別の審査(※)が行われます。
次年度、第一種SIGとなるための条件
当該年度において、全国大会における企画セッションを企画・実施し、かつ研究会における企画セッションを2回以上企画・実施していること
次年度、第二種SIGとなるための条件
全国大会もしくは研究会における企画セッションを年度内に1回以上企画・実施していること
第一種SIG、第二種SIGに共通する条件
学会誌に掲載する活動報告記事を年度末に提出していること
所定様式に基づく年度報告書を年度末に提出していること
所定様式に基づく年度報告書を年度末に提出していること
※その他、内容や規模等に基づいて総合的に審査を行います。
注意事項
提案にあたっては、JSiSEの公益性や学会活動との整合性を十分にご検討ください。
お問い合わせ
教育システム情報学会 研究活性化委員会: kasseika-ml@jsise.org